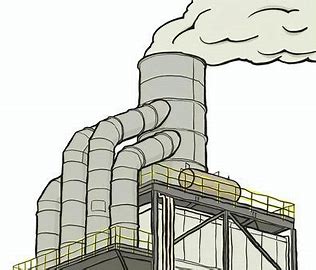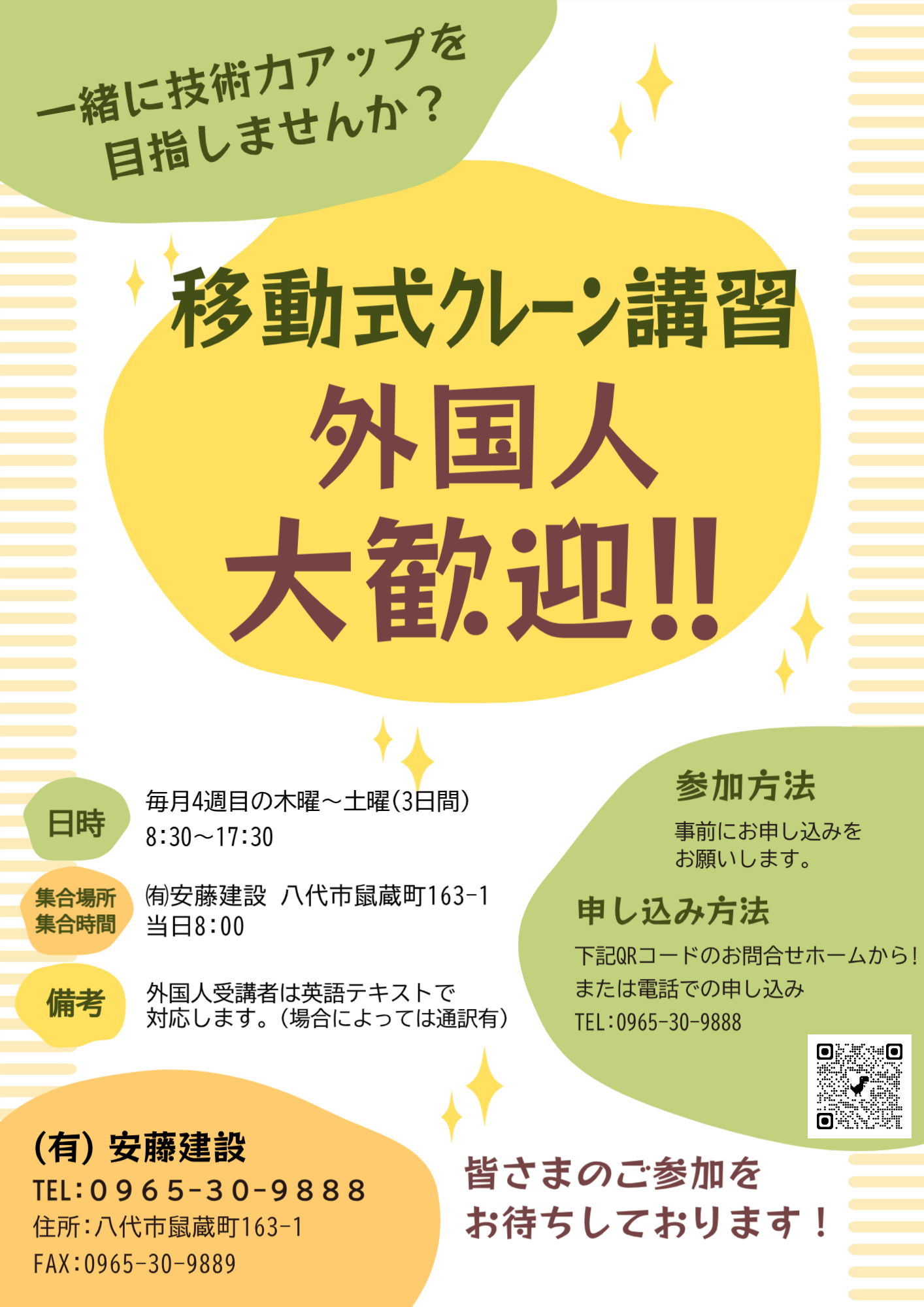-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ハンマーカンマ―HammerComma
ハッピーラッキーワンダフルレインボーイニシアチブ♪
TOM開発も福岡県で建設業の許可を取得しました~!涙嬉喜楽
たくさん建設するぞーーーーーーーーーーーーーBIGLOVE….
建設業大好き ______
TOM開発は福岡県京都郡みやこ町勝山箕田87で産業廃棄物の中間処理、収集運搬、建設業を行っております。

ハラスメントを許さない!!!
ハラスメントとは。。。。。?
ハラスメント(harassment)とは、相手に不快感を与える「いじめや嫌がらせ」によって、被害者の就業環境を悪化させる行為全般のことです。 暴力などの身体的な行為のみならず、暴言や無視といった精神的なダメージを与える行為もハラスメントにあたります。 ハラスメントはその原因によって様々な種類に分けられ、現在は50種類以上のハラスメントが存在するといわれています。
怖いですね!!
不快なことがあったときは、自分もこのような振る舞いをしていないか振り返るようになりました!☺
あたりやすい人にだけあたっていませんか?
不機嫌をふりまいていませんか?
自分がされたらどう思いますか?
余裕がないときこそ優しくできていますか?
私はぜーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーったいにハラスメントを許しません!!!!!!しません!!!!!!!!我慢もしません!!!!!!!!
㈱TOM開発は福岡県京都郡みやこ町勝山箕田87で産業廃棄物の処理、収集運搬を行っております。ハラスメントは行っておりません💛
ぜひ💛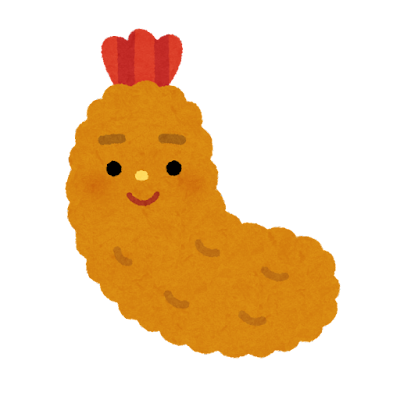
お家で実践できる「風水」
こんにちは!WithHomeお客様サポートの安藤です ^^
2月になって寒さが本格的になってきましたね、、
早く暖かくなってほしいな、と願うばかりの私です、、笑

本日のBLOGテーマは「お家で実践できる「風水」」
前回BLOGでご紹介した「縁起のいい日」もそうですが
「風水」も気にしすぎるとキリがありません、、
ですが、頭の片隅に置いておいて
家づくりや模様替えをする際に
「そういえば、ベッドはこっちに置いた方が運気が上がるって言ってたな」
といったように、参考にすると気持ちの面でも違うかもしれません ^^
今回はお家づくりにおいての「風水」ではなく
現在お住いのお家でもすぐ実践しやすい
「運気を上げる方法」をご紹介します ^^
【玄関にライト】
玄関は良い気を迎え入れ
家の中に導きいれる幸運の入口です
いわゆる家相では東・南東・南向きの方角がよいとされていますが
土地の条件によっては思い通りの位置にできないことももちろんあります
そのような場合は明るさや風通しに気をつけましょう
陰のパワーがとどまるとよくありません
明るい印象の玄関を作りにくかったのであれば
好みのライトを配置していつも明るくし
天と地、陰と陽のバランスを保つことを心がけると良いです
【水周りに観葉植物】
トイレやお風呂といった水周りはどうしても汚れがたまりやすい場所です
体を清めるお風呂や不浄なものを流すトイレは
運気を活性化する場所ではありませんが
風水を気にしない方でも清潔に保ちたい場所ですよね
鬼門と呼ばれる北東にはトイレやお風呂
キッチンなどの水周りはないほうがよいとされています
しかし、明るい東や南側にリビングダイニングを配置すると
どうしてもこれらの水周りが
北側に回ってしまうことはよくある話です
このようなときは、とにかく掃除を徹底することと
小さな観葉植物を置いてみてください
観葉植物には悪い気を吸ってよい気を出すという力があります
狭いトイレやお風呂でも壁に掛けるタイプなら場所をとりませんので
簡単に取り付けることができますよ
【階段に絵画・写真やカーテン】
階段は1階と2階・3階をつなぐ「気の流れ道」です
ここで気が穏やかに流れるよう気を付けなければなりません
薄暗く掃除が行き届いていない階段は
スムーズに気が流れません
安全面からも、暗く、掃除ができていない階段はとても危険です
水を意味する北にある階段の壁には
海や川、湖の絵画や写真がよいでしょう
また木を意味する東なら朝日や樹木のイメージ
火を意味する南なら緑や赤の色合いのイメージがマッチします
金を意味する西ならば、黄色の花の写真や絵もいいでしょう
もし階段の途中や登りきった位置に窓があるなら
レースのカーテンを付けてください
せっかくのよい気が逃げないようにするためです
階段は、登っていく先を見ながら上がるものですので
朝日や西日で目を傷めない意味もあります
【寝室にはベッドヘッドのついているベッド】
寝室は1日の疲れを取り、明日へのパワーを取り戻すために重要な部屋です
見た目にも落ち着ける雰囲気を作ることも大切ですが
陰の気が満たされている方が安眠できます
もちろん定期的に掃除・洗濯をし、清潔を保っていることも必要で
これは言うまでもありませんね
ベッドはベッドヘッドが付いている物が良いです
またベッドヘッドを壁に着けるように配置することで
潜在意識から安心して眠ることができます
今は、充電のため枕元にスマートフォンを置いている方も多いようですが
これらから発する電磁波によって気が乱れ安眠できません
この問題を解消するためにも
スマートフォンをサイドテーブルの引き出しの中にしまう
足元に設置するなど、枕元から離れた位置に置くようにしましょう
木や木綿などナチュラルな素材に囲まれて眠ることも大切です
いかがでしょうか?
今回ご紹介したものは家づくりの中も実践できますが
現在お住いのお家でも実践できると思います ^^
風水は気持ちの問題だ!とおっしゃる方もいらっしゃると思いますが
少し気にするだけで安心して暮らせる、と思えば
それも一つの手段だな、くらいで思っていただければと思います ^^

縁起のいい日の参考に「二十八宿」
こんにちは!WithHomeお客様サポートの安藤です ^^
今週は大寒波が訪れた一週間でしたね!
弊社でもかなりお久しぶりに雪が見れて少し嬉しかった私です。笑

今回のBLOGテーマは「縁起のいい日の参考に「二十八宿」」
お家づくりのセレモニーでよく意識される「お日柄のいい日」
決める際には有名な「六曜」や他にも「十二直」という考え方もあると
前回のBLOGにてお伝えいたしましたが
他にも「二十八宿」というものもあるのです!
二十八宿(にじゅうはっしゃく)とは
中国の天文学・占星術で用いられていた考え方で
その吉凶をいまからご説明させて頂きます♪
お家づくりに関係する日には” “をつけています
角(かく)
【吉】着始め・“棟上げ”・普請造作・結婚
【凶】葬式
亢(こう)
【吉】衣類仕立て・物品購入・種まき
【凶】“造作”・“不動産売買”・移転・旅立ち等
氐(てい)
【吉】結婚・開店・結納・酒造り
【凶】着始め・葬儀・水に近づく
房(ぼう)
【吉】髪切り・結婚・旅行・移転・開店・祭祀・婚礼
“棟上げ”・移転・”造作”に大吉
【凶】告訴・不倫など
心(しん)
【吉】祭祀・移転・旅行・新規事業
【凶】結婚・葬送。“造作”大凶。盗難注意
尾(び)
【吉】結婚・開店・移転・“造作”・新規事業
【凶】着始め・仕立て・葬送
箕(き)
【吉】“動土”・池堀り・仕入れ・集金・“改築”
【凶】結婚・葬式
斗(と)
【吉】“土掘り”・開店・造作に吉
【凶】他は悪し
牛(ぎゅう)
【吉】移転・旅行・金談など全て。特に正午は大吉祥
女(じょ)
【吉】稽古始め・お披露目に
【凶】訴訟・結婚・葬式。葬儀は大凶。
虚(きょ)
【吉】着始め・学問始め
【凶】相談・“造作”・積極的な行動。相談事は大凶
危(き)
【吉】“壁塗り”・船普請・酒造り
【凶】衣類仕立て・“高所作業”
室(しつ)
【吉】祈願始め・結婚・祝い事・祭祀・移転・井戸掘り
【凶】葬式・遠出
壁(へき)
【吉】開店・旅行・結婚・衣類仕立て・新規事業開始
“造作”は大吉
【凶】南に行く
奎(けい)
【吉】開店・文芸開始・樹木植替え・衣類の裁ち縫い
“棟上げ”・旅立ち・婚礼等万事大吉
【凶】開店など新規の事・訴訟・交渉など
蔞(ろう)
【吉】“動土”・“造作”・縁談・契約・“造園”
とくに衣類の裁ち縫いは長生きの良薬
【凶】開店など新規の事・訴訟
胃(い)
【吉】開店・移転・求職
【凶】“造作”・葬儀。衣類裁断は大凶
昇(ぼう)
【吉】神仏詣で・祝い事・開店
【凶】衣類裁ち・“増改築”
畢(ひつ)
【吉】祭祀・取引開始・普請開始・土地開拓・“造作”等
【凶】衣類裁ち
觜(し)
【吉】稽古始め・運搬始め
【凶】“造作”・衣類着始め
参(しん)
【吉】仕入れ・納入・取引開始・祝い事・縁談・養子取り・“造作”
【凶】衣類裁ち
井(せい)
【吉】神仏詣で・種まき・“動土”・“造作”
【凶】衣類仕立てに凶。衣類裁ちは離婚の原因に
鬼(き)
【吉】二十八宿中最大の吉運の日。すべて大吉
【凶】婚礼は凶
柳(りゅう)
【吉】物事を断る
【凶】結婚・開店。特に葬式は不幸が重なり大凶
星(せい)
【吉】運転始め・“便所改造”
【凶】祝い事・種まき
張(ちょう)
【吉】就職・見合い・神仏祈願・祝い事。種まきに大吉
【凶】衣類裁断・“樹木を切る”など
翼(よく)
【吉】耕作始め・植え替え・種まき
【凶】“高所作業”・結婚
軫(しん)
【吉】“地鎮祭”・“棟上げ”・落成式・祭祀・祝い事
【凶】衣類仕立て・旅行
このほかに「一粒万倍日」「天赦日」「不成就日」「三隣亡」といった
年に数回~数十回の吉凶日が混ざってきます
かつて縁起の良さから「一粒万倍日」を選んで
入籍された有名人がいらっしゃって、その日を調べてみたら
「一粒万倍日」「先勝(六曜)」「破(十二直)」「壁(二十八宿)」でした
「先勝」なので午前中は良く、縁起のいい「一粒万倍日」ですが
「破」なので婚礼や祝い事には凶とされる日です
「壁」も婚礼に大吉という吉凶混合の日でした、、
『縁起日』にはそれぞれ全くべつの由来があり、優劣はありません!
また、全てに揃って吉になる日を探してもほとんどないのです
こだわりすぎるとお家づくりが進まなくなってしますので
ゲンを担ぐための1つの参考くらいで考えた方がいいと思っております ^^



 また経過をお知らせいたします。
また経過をお知らせいたします。